【脱・自己流】報告書・資料作成を劇的に効率化する「型」の力
報告書や会議資料の作成に、毎回頭を悩ませていませんか?「何から書けばいいのか」「どう構成すれば分かりやすいのか」…そんな悩みを抱えるあなたにこそ知ってほしいのが「型」の活用です。本コラムでは、報告書や資料作成の時間を大幅に短縮し、内容の質を高めるための効果的な「型」と、その活用方法を具体的に解説します。自己流から脱却し、「型」を味方につけて、スマートな資料作成を実現しましょう。
資料作成の前に考えるべき「三つの輪」
資料作成に取り掛かる前に、必ず意識しておきたい3つの要素があります。それは「目的」「読み手」「情報」です。これら3つの要素は相互に深く関連しており、それぞれを明確にすることで、資料の方向性が定まり、無駄な作業を減らすことができます。
まず「目的」です。この資料は何のために作成するのでしょうか?意思決定を促すため、情報共有のため、進捗状況を報告するためなど、資料の役割を明確にすることで、盛り込むべき内容や表現方法が見えてきます。
次に「読み手」です。誰に向けてこの資料を作成するのでしょうか?上司、同僚、取引先など、読み手の知識レベルや関心事を考慮することで、より効果的に情報を伝えることができます。専門用語を避ける、図やグラフを多用するなど、相手に合わせた工夫が重要です。
そして「情報」です。資料に盛り込むべき情報は何か?必要なデータは揃っているか?情報の過不足がないかを確認することで、資料の信頼性を高めることができます。客観的なデータや事実に基づいた情報を整理し、論理的に構成することが求められます。
この「目的」「読み手」「情報」の三つの輪を意識することで、資料作成の軸が定まり、より効率的で質の高い資料作成が可能になります。
報告書作成の基本「PREP法」
報告書作成において、論理的で分かりやすい構成は非常に重要です。そこでおすすめしたいのが「PREP法」と呼ばれる構成テンプレートです。PREP法は、Point(結論)、Reason(理由)、Example(具体例)、Point(再結論)の頭文字を取ったもので、簡潔かつ説得力のある報告書を作成するのに役立ちます。
まず「Point(結論)」では、最も伝えたい結論や主張を冒頭に述べます。これにより、読み手は報告書の要点を最初に理解することができ、その後の内容をスムーズに把握することができます。
次に「Reason(理由)」では、結論に至った理由や根拠を具体的に説明します。客観的なデータや分析結果を示すことで、結論の説得力を高めることができます。複数の理由がある場合は、箇条書きなどで整理すると分かりやすくなります。
続いて「Example(具体例)」では、理由を裏付ける具体的な事例やデータを示します。抽象的な説明だけでなく、具体的な事例を挙げることで、読み手の理解を深めることができます。グラフや図などを活用するのも効果的です。
最後に「Point(再結論)」では、冒頭で述べた結論を改めて強調します。理由と具体例を踏まえた上で、改めて結論を提示することで、メッセージをより強く印象づけることができます。今後のアクションや提言などを加える場合もあります。
PREP法を活用することで、報告書全体の構成が明確になり、論理的な流れを作り出すことができます。読み手にとっても理解しやすく、説得力のある報告書作成に繋がるでしょう。
会議資料作成の鉄則「1スライド1メッセージ」
会議資料は、参加者に対して効率的に情報を伝え、議論を活性化させるための重要なツールです。そのためには、「1スライド1メッセージ」という鉄則を守ることが重要です。
一つのスライドには、一つの主要なメッセージやテーマを絞って記載します。情報を詰め込みすぎると、かえって内容が伝わりにくく、参加者の集中力を低下させる原因となります。
各スライドでは、伝えたいメッセージを明確に示し、それを裏付けるデータや図、グラフなどを簡潔に配置します。文字情報は必要最小限に留め、視覚的な要素を効果的に活用することがポイントです。
例えば、売上報告の資料であれば、「今月の売上は〇〇%増加しました」という主要なメッセージをスライドのタイトルに大きく表示し、その理由や内訳をグラフで分かりやすく示すといった具合です。
また、スライド全体のデザインにも配慮が必要です。フォントの種類やサイズ、色使いなどを統一し、見やすく、理解しやすい資料作成を心がけましょう。アニメーションやトランジション効果は、多用すると逆に見づらくなる場合があるので、目的に合わせて適切に使用することが重要です。
「1スライド1メッセージ」を意識することで、会議参加者は資料の内容をスムーズに理解し、活発な議論に繋げることができます。
資料作成を効率化する「テンプレート」活用術
日々の資料作成業務において、同じような形式の資料を何度も作成する必要がある場合、テンプレートの活用は非常に有効な手段です。報告書、会議資料、提案書など、用途に応じたテンプレートを作成しておくことで、資料作成にかかる時間を大幅に短縮することができます。
テンプレートには、タイトル、日付、作成者などの基本情報はもちろん、見出しのスタイル、フォントの種類やサイズ、グラフの形式などをあらかじめ設定しておくことができます。これにより、毎回ゼロから資料を作成する手間が省け、内容の作成に集中することができます。
また、組織内で共通のテンプレートを使用することで、資料の品質を一定に保ち、ブランドイメージの統一にも繋がります。過去の優れた資料を参考に、自社のニーズに合ったオリジナルのテンプレートを作成するのも良いでしょう。
Microsoft PowerPointやGoogle Slidesなどのプレゼンテーションソフトには、豊富なテンプレートが用意されています。これらのテンプレートをそのまま利用するだけでなく、自社のロゴやカラーを取り入れるなど、カスタマイズすることも可能です。
テンプレートを定期的に見直し、改善していくことも重要です。利用者のフィードバックを参考に、より使いやすく、効率的なテンプレートへと進化させていきましょう。
資料の品質を高める「推敲」の重要性
資料作成の最終段階として、必ず行っておきたいのが「推敲」です。推敲とは、作成した資料を客観的な視点で見直し、修正を加える作業のことです。誤字脱字、文法の誤り、表現の不自然さなどを修正することで、資料の信頼性と分かりやすさを向上させることができます。
資料を作成直後は、作成者の主観が強く働いているため、ミスに気づきにくいものです。時間を置いてから見直す、第三者にチェックしてもらうなど、客観的な視点を取り入れることが重要です。
声に出して読んでみるのも効果的な推敲方法の一つです。文章の流れやリズム、言葉の響きなどを確認することで、読みにくい箇所や表現の改善点を見つけやすくなります。
また、資料全体の構成や論理展開に矛盾がないか、目的や読み手に合致した内容になっているかなども、改めて確認する必要があります。必要に応じて情報の追加や削除、表現の変更などを行います。
推敲を丁寧に行うことで、資料の完成度が格段に向上し、相手に正確かつ効果的に情報を伝えることができます。資料作成の最後の仕上げとして、十分な時間を確保するようにしましょう。
まとめ
報告書や会議資料の作成は、ビジネスパーソンにとって避けて通れない業務の一つです。「型」を活用し、効率的な作成プロセスを確立することで、資料作成にかかる時間と労力を大幅に削減し、より質の高い資料を作成することができます。今回ご紹介した「三つの輪」「PREP法」「1スライド1メッセージ」「テンプレート」「推敲」といった考え方や手法を、ぜひ日々の資料作成に取り入れてみてください。自己流から脱却し、「型」を味方につけることで、あなたの資料作成スキルは飛躍的に向上するはずです。
プリントモールでは、報告書や会議資料の印刷・製本を高品質かつスピーディーに行っています。用途や予算に合わせた様々なオプションをご用意しており、お客様の資料作成をトータルでサポートいたします。資料作成でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
冊子印刷なら ネット印刷プリントモール
https://printmall.jp
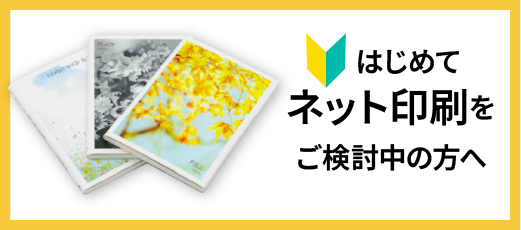
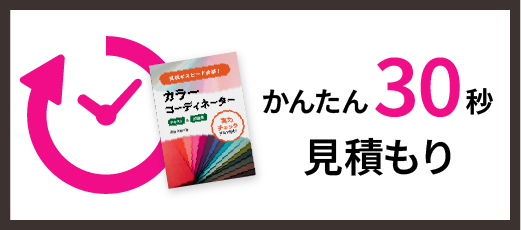

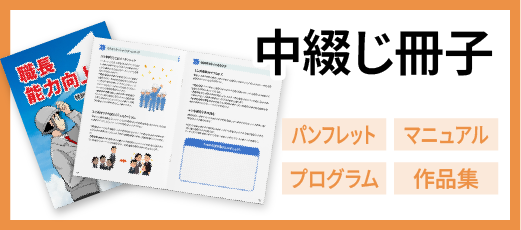
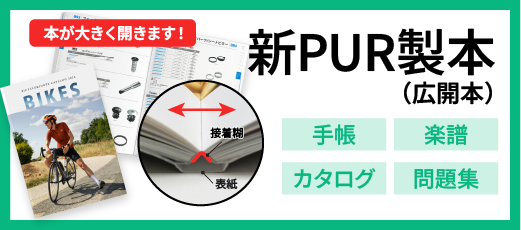



 お問合せ
お問合せ